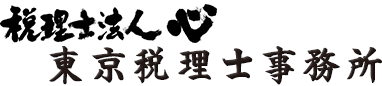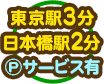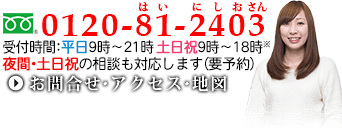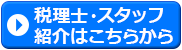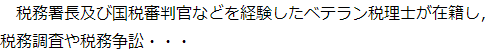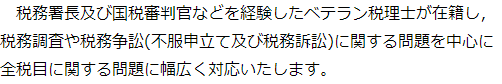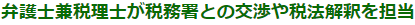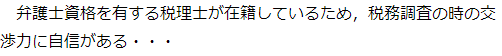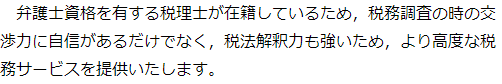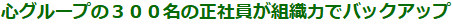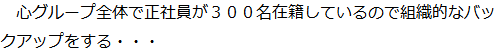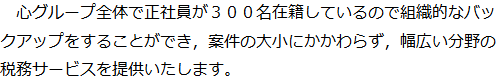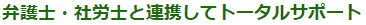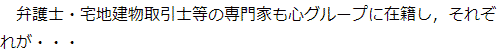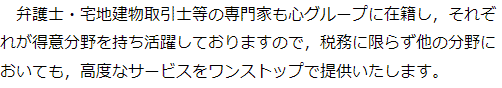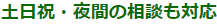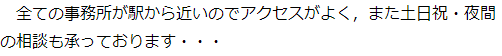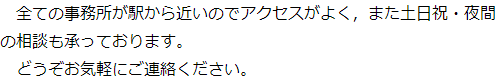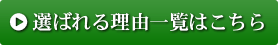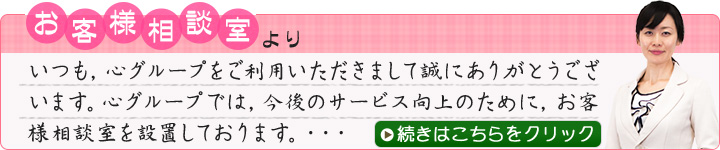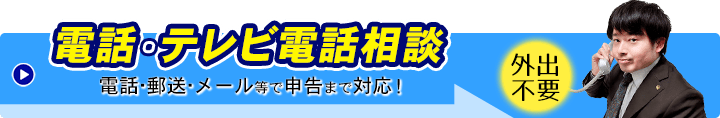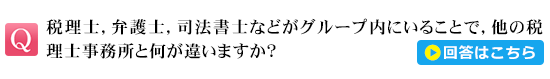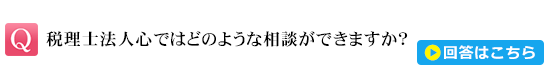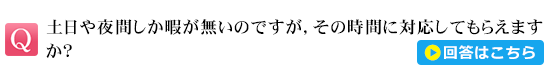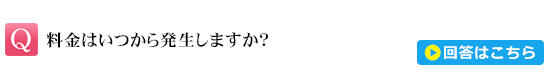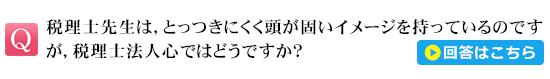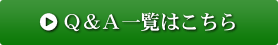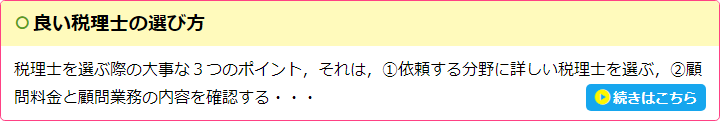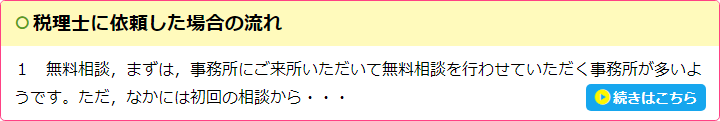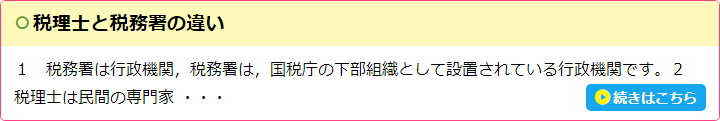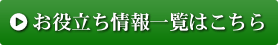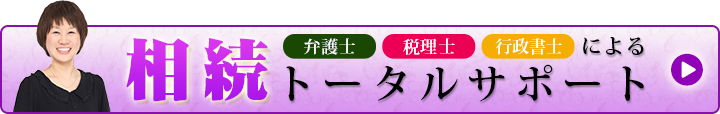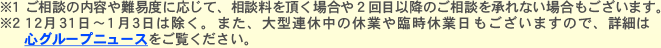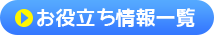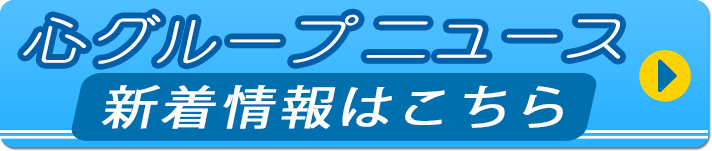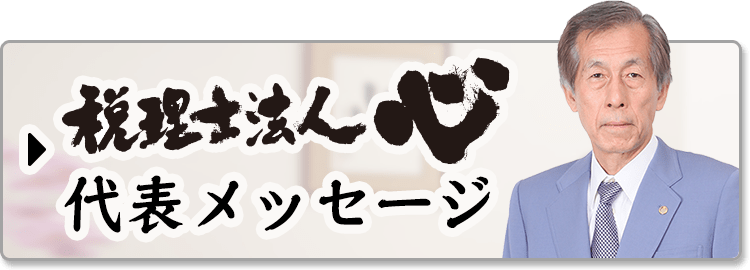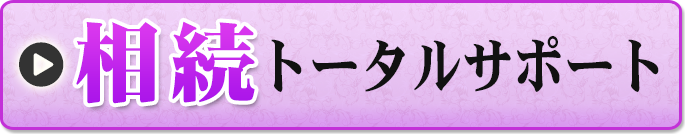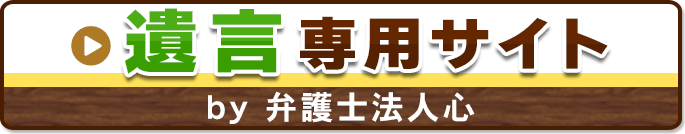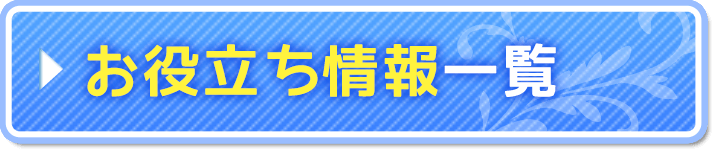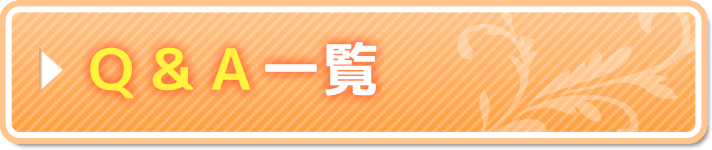東京駅の近くにある事務所です
税理士法人心 東京税理士事務所は、東京駅から徒歩3分と、来所いただきやすい場所にあります。詳しい場所はこちらからご確認ください。
税理士と顧問契約を結ぶメリット
1 税理士と顧問契約
税理士と顧問契約を結ぶことは、特に中小企業や個人事業主にとって多くのメリットがあります。
以下に税理士と顧問契約を結ぶ具体的なメリットをいくつか説明していきます。
2 顧問税理士と税務の専門的サポート

事業を営んでいると、お金を扱う以上、必ず税務的な問題は日常的に発生します。
しかし、税法は毎年のように改正されるので、その改正について一人で調べようとするとたくさんの時間がかかります。
そのてん、税理士は税務の専門家であり、常に最新の税法に精通しています。
そのため、顧問税理士から税務のサポートを受けることで、適正な税務申告を行うことができ、過少申告や過大申告を防ぎ、税務調査のリスクを軽減することができます。
また、顧問税理士は、継続的に納税者と関与しますので、適切な節税対策を提案することができ、経営者の税負担を軽減できる可能性が高まります。
税理士と顧問契約を結ばず、年に1回確定申告書の作成のみを依頼する場合には、基本的には、決算期が終わってから税金の計算をするだけになりますので、節税対策を提案することは難しいと言えます。
3 顧問税理士と会計サポート
事業をしていれば、毎日売上金がはいり、経費を使う必要があります。
にも関わらず、お金の流れが管理できていなければ、事業を行うことはできません。
正確な会計処理と財務管理は、健全な経営に絶対に必要なことと言えます。
顧問税理士は、通常、日々の取引記録を正確に行い、帳簿を作成し、会計業務の負担を減らします。
また、決算期末の決算処理等をサポートし、決算書の作成を行います。さらに、顧問税理士は、日々のキャッシュフローを分析し、経営改善
のための具体的な提案を行うこともできます。
4 顧問税理士のメリット
このように、会計・税務業務について、顧問税理士という専門家にまかせることで、社内の業務を効率化します。
そして、経営者が本業に専念できるような環境を整えます。
顧問税理士は、年に1回だけ決算時期にかかわる税理士と比較して、事業の状況を深く理解することができ、より的確なアドバイスが可能になります。
税務、会計、経営、法務など多岐にわたる分野で顧問税理士から専門的なサポートを受けることができます。
このような点から、税理士との顧問契約は事業の成功と安定した経営のために必要な投資といえます。
税理士の選び方
1 ご依頼は相談したい分野を集中的に扱っている税理士へ

一言に税理士といっても、その取扱分野には様々な種類があります。
税金の種類ごとに異なる法律があり、分野が変われば必要になる知識も全く別のものになってきます。
加えて、すべての税理士があらゆる分野に詳しいとは限りません。
税理士試験も選択科目制であるため、試験科目で選んでいなくとも、のちに専門分野にすることはできますが、すべての税金の分野について勉強をしなくとも税理士になることはできます。
そのため、税理士だからといって、あらゆる税務上の問題を完璧に解決できるわけではなく、それぞれに主に扱っている分野や得意分野があります。
そこで、税理士に依頼する際には、その税理士の主要な取扱分野が何かということを意識する必要があります。
2 税理士の力量により納税の金額が変わってくることも
税理士の仕事は、税金の申告をするだけで誰がやっても同じになると考えられがちです。
しかし実際は、どの税理士に依頼するかによって、支払う税金の金額が大きく変わることがあります。
税金には減税の特例があり、これを利用することで支払う税金を大きく減らすことができます。
もっとも、特例は多種多様で、併用できるものや併用できないものがあるため、利用する特例により税金の額は大きく変わってきます。
最大限に節税するため、どの特例を使うか、どの特例を組み合わせるかは、税理士の腕の見せどころです。
その税分野に詳しければ詳しいほど、多くの選択肢の中から検討し最も良い提案をすることができます。
3 専門の税理士ほど料金が安いことも
「専門性が高くサービスが充実しているほど、料金が高くなるのではないか?」という疑問を抱かれる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、必ずしも専門性が高いほど料金が高くなるというわけではありません。
取扱分野を絞っている税理士ほど、分野を絞って効率的に処理をしますし、作業に慣れているため、スピードが早いです。
それゆえ、同じ作業でも、分野を絞っている税理士の方がより早く多くの業務をこなせるため、料金を下げることも可能です。
そのため、専門で取り扱っている税理士ほど、安く早く依頼を完了できる可能性があります。
4 税理士選びにお悩みの際はまずはお気軽に無料相談を
税理士の選び方でお困りの方は、まずは当法人のフリーダイヤルへお気軽にご連絡ください。
ご相談内容に応じて、その分野を集中的に取り扱う担当の税理士がお話をお伺いします。
税理士の取扱分野
1 税理士が取り扱う分野

税理士は、所得税でも法人税でも相続税でも、どの税分野でも税務業務を行うことができます。
自分の主に取り扱っている分野以外でも、頼まれれば仕事を請け負うことが多いです。
ただし、すべての税理士がすべての分野において精通した知識と経験を持っているわけではありません。
2 税理士試験で扱われる分野
税理士試験においては、税務分野の全科目の試験を受けて合格するという必要はなく、全科目の試験を受けなくても税理士になることができます。
税法の科目としては、所得税法又は法人税法のいずれか1科目に合格し、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税の中から選択して2科目合格できれば、税理士になれる可能性があります。
そのため、試験において選択しなかった分野を全く勉強していないため、全く詳しくない分野を持つ税理士も存在することになってしまうのです。
3 実務経験としてあまり取り扱われない分野もある
試験だけでなく、実務経験においても、全税目を満遍なく経験している税理士というのも実は少ないです。
なぜなら、実務経験を積めるだけの仕事量が実際にあるとは限らないからです。
例えば、相続税申告は全国で年間15万件程度行われていますが、これに対し、全国の税理士登録者数は約8万人います。
つまり、単純に税理士の数で頭割りすると、各税理士が年間1、2件程度の実務経験しか積めないことになってしまいます。
このように、十分な実務経験を積めない状態になってしまっているという実態もあります。
4 同じ税目の中で注力分野を持っている税理士もいる
さらに、同じ税目の中でも、ある部分に特化している税理士もいます。
例えば所得税の分野において、太陽光発電に関する申告ばかり行っている、多数のマンションを所有している方の不動産所得に関する申告ばかり行っている、接骨院の個人事業主の申告ばかり行っているといった、業種に特化して注力している分野を持っている税理士もいます。
注力している分野であれば、税理士がその分野の最新情報や分野独自の情報を把握している可能性が高いため、ご自分が相談したい税目や業種が得意な税理士に相談をすることをおすすめします。
税理士に相談すべきケース
1 誰にでも税理士への相談が必要になる可能性がある

税理士に相談するのは、経営者や資産家の方ばかりではありません。
サラリーマンの方も所得税を支払っていますし、住宅を購入・売却する際などには多額の税金が発生することもあります。
そのような場合に、個人の方でも事業者の方でも、申告時の注意点を聞いたり、代わりに申告作業を依頼したりできます。
税金を支払いながら生活している以上、誰しもが税理士へ相談する必要が生じる可能性があるのです。
なお、どのケースにおいても、税理士に相談するためには、税理士に相談の前提となる情報を共有する必要があります。
情報の共有ができていないと、相談内容は不完全または不正確なものとなってしまったり、算出される税額が間違ったものになってしまい、加算税や延滞税が発生してしまうリスクもありますので、ご注意ください。
以下では、税理士へ相談すべきケースについていくつかご紹介していきます。
2 所得税や法人税について税理士に相談すべきケース
個人事業主も法人も、収入と経費を計算する必要がありますが、何が経費に該当するのか、どこまでが経費になるのかという判断に迷うことがあります。
事業規模が大きくなって取引が多くなり、税務処理に時間がかかってしまう、税務処理の判断に迷うことが多くなったというケースは、税理士に相談すべきだといえます。
3 相続税について税理士に相談すべきケース
相続税の申告をする場合は、すべての遺産を把握して、価額を評価する必要があります。
また、相続税が課税される財産と課税されない財産があるため、それらを判断した上で、財産の価値を評価しなければなりません。
そのため、相続税が課税される財産の範囲が分からない方は、税理士に相談するとよいかと思います。
例えば、死亡保険金は相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税が課税され、課税額の計算において基礎となります。
また、名義預金の疑いがある財産が存在し、生前に相続人に現預金を移動させている場合には、どのやりとりが相続税あるいは贈与税の対象となるかについて検討する必要があります。
こうしたケースにおいて税理士へ相談することで、相続税なのか贈与税なのか、判断を仰ぐことができます。
他にも、土地の価額を評価する際には、土地の形や大きさ、周辺の状況、土地上の権利等の事情を考慮して計算をする必要がありますし、特例の適用によって大幅な評価額の減額を行うことができる場合もあります。
そのため、相続財産の中に土地が存在するケースでは、税理士に相談することでより正確な申告が可能になるといえます。
他士業と協力できることの強み
1 税理士と弁護士が協力できることの強み

⑴ 揉め事になっても安心
税理士をはじめとする弁護士以外の士業は、揉め事の仲裁や解決には関わることができません。
しかし、税金の申告を関係者で共同して行おうとしていたところ、その途中で関係者同士が揉め始めてしまうケースはしばしばあります。
税理士は揉め事の仲裁や解決のための交渉をすることができませんので、揉め事が起こると手続きを進めることができなくなってしまいます。
揉め事になると、「この件は、関係者の皆さんで話し合って解決してください。」と言って、手を引いてしまう税理士もいるようです。
このような場合、弁護士に依頼するしかありませんが、揉め事が起きてから弁護士を探し始めるのは二度手間になりますし、時間を要するため早期解決が遠のいてしまいます。
税理士と弁護士が協力している事務所の場合は、事前に情報を共有することでスムーズに対応できるうえ、場合によっては揉め事が大きくなる前に弁護士に依頼することで、早期に解決することができる場合もあります。
⑵ 裁判所の手続なども利用が可能
裁判所を利用する手続などを代理で行うことは、原則として弁護士しか認められていません。
また、生前対策のために遺言書を活用するケースは多くありますが、遺言書の相談・作成も弁護士しかできません。
そこで、これらの手続を利用する場合、税理士と弁護士が連携すれば、士業同士で、正確に漏れなく情報を共有することができます。
また、依頼する側としても、両者に情報を伝える必要はなく1つの窓口とやり取りをするだけで済みます。
さらに、連携がスムーズにできるため、早期の解決を図ることができます。
2 税理士と司法書士が協力できることの強み
司法書士の仕事といえば、法務局での登記手続です。
しかし、税理士が主導する生前対策でも、司法書士の出番は多くあります。
例えば、生前対策の1つとして、家族信託を利用する場合、信託には法務局での登記手続が必須であるため、司法書士が必要になります。
また、不動産管理会社を設立して節税対策を行う場合は、不動産の名義変更のための登記手続、不動産管理会社の法人登記が必要になりますので、ここでも司法書士の出番があります。
このように、税理士と司法書士の仕事は密接に関連していますが、それぞれが連携することで、スムーズに最善の解決策を提案することができます。
税理士法人心の特徴
1 国税OB税理士が在籍

当法人には、税務署長及び国税審判官などを歴任した経験豊富な税理士が在籍しております。
税務署の内部の仕組みだけでなく、税務調査に向けてどの程度資料収集をしてくるのか、どのような観点から税務調査を行うかを熟知しています。
このため、税務調査になった際に、どのような点に留意して対応すればよいのかについて、より適切に方針を立てて対応することができます。
また、あらかじめ、税務調査時のポイントを想定できることにより、申告の際、どのような点に留意して説明を行ったり、資料を準備したりすればよいのかについても配慮することができますので、そもそも税務調査に入られる可能性の低い、適正な申告を行うことを期待していただくことができます。
2 弁護士資格を有する税理士
当法人には、単に税理士資格を有しているだけでなく、弁護士資格も有している税理士が複数います。
弁護士であれば、法律のプロとして、税法、審判例に基づき的確に反論することが可能です。
また、弁護士は、普段から業務として示談交渉や和解交渉を行っているため、税務調査の時にも、税務調査をどのように収めるか、指摘事項のうち税務署にどこまで妥協させることができるかといった交渉の方針を的確に立てることができます。
その上で、方針どおりに調査の場を納めるにはどうしたらよいか、戦略を立てて交渉することができます。
このため、より高度な税務サービスを提供させていただくことが可能であると考えます。
3 弁護士、社労士、宅地建物取引士との連携
単に、税理士業務だけにとどまらず、グループ企業に在籍している各種専門家と協力することで、幅広い領域での業務に対応可能です。
事業を行う上で紛争が発生した場合には弁護士、労働・社会保険に関する相談があれば社労士、不動産の売買・仲介のご希望があれば宅地建物取引士と協力して、ワンストップのサービスを提供させていただきます。
4 土日祝日、夜間の相談も可能
普段のお仕事が忙しく、平日、日中に税理士に相談する時間を作ることが難しいという方もいらっしゃいます。
当法人では、そのようなお客様のために、土日祝日、または、夜間の相談も承っております。
相談の日程のご希望がありましたら、遠慮なさらずにご希望をお伝えください。
税理士に相談・依頼するタイミング
1 事業開始前のタイミング

会社設立のタイミングだと、まだ事業規模が小さく、ご自身で経理業を行われる方も多いと思われます。
しかし、最初に誤った経理処理で進めてしまうと、後々誤った処理の金額が積み重なり大きな金額となってしまう可能性があります。
その誤った処理を税務調査の際に指摘されれば、通常支払うべき税金の他に、過少申告加算税や延滞税といったペナルティも課される危険性があります。
このタイミングで税理士に依頼すれば、誤った処理を防ぐことができ、決算や確定申告の際もよりスムーズに作業できるかと思います。
また、事業開始の際に知っておかないと、税金を無駄に多く払うことになりかねない事柄もあります。
正しく経理業務を行うため、また、無駄な税金を支払わないようにするために、事業開始前に税理士に相談することをおすすめします。
2 事業開始後決算または確定申告時期
事業開始前に税理士に相談しなかった場合、次の相談のタイミングとしては、会社の場合は決算、個人事業主の場合は確定申告の時期になります。
会社の場合は、決算期末から2か月以内に、個人事業主の場合は、翌年3月15日までに申告をする必要があります。
申告書では、1年間の売上と経費を集計し、利益を確定する必要があります。
日々の経理業務や帳簿作成はできるものの、申告書の作成が複雑でご自身ではできないという場合には、税理士に相談する必要があります。
ただし、決算のタイミングで、申告書作成のみを税理士に依頼するということは、毎月の経理業務を税理士が把握できないため、税理士が効果的な税金に関するアドバイスをすることが難しい場合もありますし、これらのタイミングは税理士の繁忙期でもありますから、ケ-スによっては依頼を断られてしまう可能性もあります。
そのため、相談や依頼のタイミングとしてはあまりおすすめできません。
3 法人成りのタイミング
個人事業主の場合に作成する確定申告書と、法人が申告に当たり作成すべき決算書は複雑さが異なります。
そのため、個人事業主が法人成りするタイミングは、税理士に相談すべきタイミングともいます。
また、法人成りのタイミングとしては、個人事業主としての利益が多くなり、所得税よりも法人税の方が低くなるタイミング、また、売上が1000万円を越え課税事業者になるタイミング等がおすすめのこともあります。
いつ法人成りをするのがよいのか、そのタイミングを検討するためにも、法人成りを検討し始めたら税理士に相談することをおすすめします。
税理士に依頼した場合の料金
1 税理士報酬の歴史的経緯

税理士に相談したいけれど、どの程度料金がかかるのかが分からず、相談をためらっている方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、税理士に支払う料金について説明していきたいと思います。
以前は、日税連の旧税理士報酬規程という税理士会が定めた基準があり、税理士の報酬体系もその基準に縛られていました。
しかし、現在ではその規程は廃止され、税理士は自由に報酬を決めることができるようになりました。
そのような歴史的経緯があり、そのまま旧税理士報酬規定に基づいた金額の税理士事務所も多いです。
とはいえ、報酬を相場よりも高くしているところもあれば、相場より低くしているところもありますので、現在では報酬の決め方も事務所によって様々となっています。
2 所得税の税理士報酬の目安
日税連の旧税理士報酬規程における所得税の税理士報酬を参考にご紹介していきます。
税理士報酬は、大きく分けて税務代理報酬と税務書類作成報酬に分かれます。
税務代理は、税務署とのやり取りをすることで、申告書の提出や申告書に関する税務署からの問合せに対応することをいいます。
税務書類作成は、所得税の申告書や申告書に添付すべき明細書等を作成することをいいます。
税務代理報酬の目安としては、以下のとおりで、年間の売上金額や所得金額に応じて変わります。
[総所得金額基準] [年取引金額基準]:
200万円未満 2,000万円未満:60,000円
300万円未満 3,000万円未満:75,000円
500万円未満 5,000万円未満:100,000円
1,000万円未満 1億円未満:170,000円
2,000万円未満 2億円未満:255,000円
3,000万円未満 3億円未満:300,000円
5,000万円未満 5億円未満:400,000円
5,000万円以上 5億円以上:450,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに:2.5万円を加算
なお、税務書類作成報酬は、上記の税務代理報酬額の30%相当額とされています。
3 依頼前にしっかりと費用を確認することが大切
上記の税理士報酬はあくまで目安ですし、この規定とは大きく異なる報酬体系の事務所もあります。
また、同じような費用だったとしても、税理士によってどこまで対応してもらえるかが違うこともあります。
後悔しないために、税理士に依頼する前には、税理士報酬の見積もりと業務範囲をしっかりと確認することが大切です。