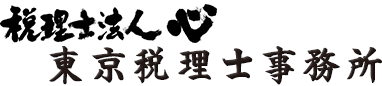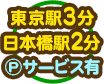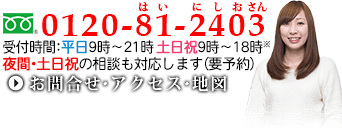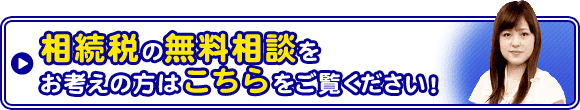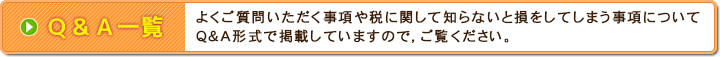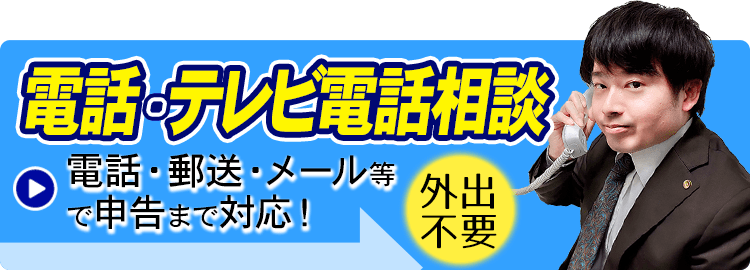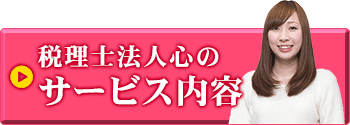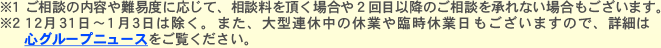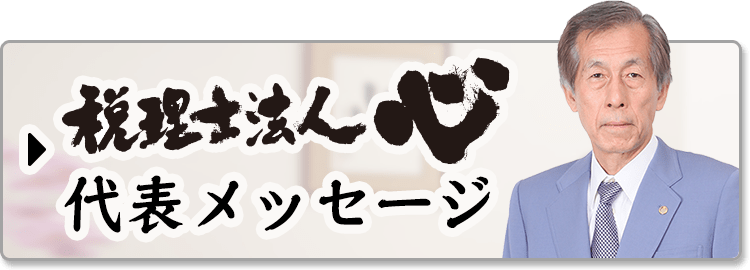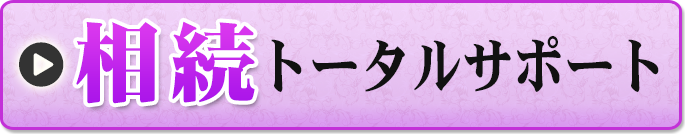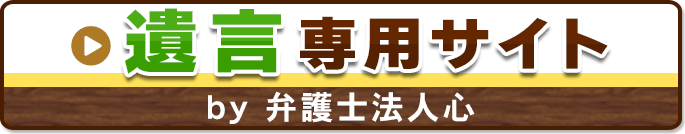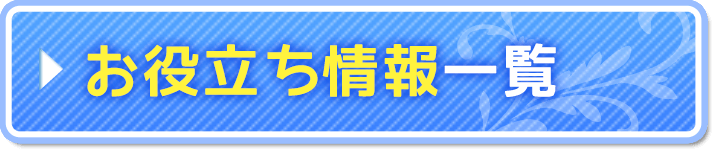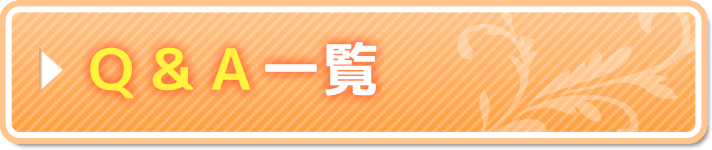相続税申告の流れ
1 必要資料の収集
まず、相続人と相続財産の内容を確認するため、資料を集める必要があります。
集める資料は、相続人が亡くなった方とどのような血縁関係にあるか、どのような種類の財産があるかによって異なってきます。
例えば、戸籍謄本、預金残高証明書、預貯金の通帳、遺言書、保険金支払通知書、固定資産課税台帳(名寄帳)、固定資産税評価証明書、固定資産税・都市計画税の納税通知書、葬式費用の領収書といった資料が必要となります。
2 相続税額の計算
集めた資料を基に、相続税額を計算します。
相続税の計算は、①課税遺産総額を計算し、②その課税遺産総額について各相続人等が法定相続分で分割したものと仮定して、相続税額の総額を算出し、③その総額を実際の遺産の取得額に応じて按分するというステップで行います。
この計算過程において、そもそも課税の対象となる財産は何か、課税対象から控除できるものはあるか等について確認する必要があります。
例えば、「死亡保険金」や「退職金」等は本来受取人の財産であり相続財産ではありませんが、相続によって取得したものとみなされ、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
一方で「死亡保険金」や「死亡退職金」のうち、一定の金額(500万円×法定相続人の数)までは非課税となりますので、その非課税額の限度で課税対象から控除します。
死亡保険金と税金の関係については、こちらで詳しく解説しております(参考リンク:生命保険の受取り時にかかる税金)。
また、被相続人の債務と被相続人の葬式に際して相続人が負担した「葬式費用」は相続財産の価額から控除されます。
最後に、相続税では、3000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除が認められていますので、債務控除や基礎控除額がいくらになるかについても、資料を基に確認する必要があります。
投資信託を売買したときの税金について 生命保険の受取り時にかかる税金